北海道文学を中心にした文学についての研究や批評、コラム、資料及び各種雑録を掲載しています
。
電話でのお問い合わせはTEL.
〒
勝手にwebいまさら探検隊column
勝手にweb「つぶやき」と「いまさら探検隊」3 2005〜2006
<技術の卓越性とオーラの有無と>
秋来ぬと目にはさやかに見えねども。風に吹かれて、ぶらりと外に出る。時は10月2日の日曜日。自宅から近くにある日本清酒の工場前に行くと、「丹頂蔵祭り」をやっていた。ここは「千歳鶴」という銘柄で親しまれている老舗。私が以前いた旭川にある名門・高砂酒造を実質的に買った酒屋でもある。
もう10数年前に前になる。中古の自動車を持っていたものの、駐車場のない私は日本清酒の工場敷地の駐車場を月1万2000円と消費税360円で借りていたのである。街中ではほどほどの値段であり、便利に使わせてもらった。いわば私にとっては車の大家さんが千歳鶴なので、いささか懐かしい。
殺風景だったスペースには酒ミュージアムという宣伝用の施設が建ち、向かいにはミュージアム・アネックスというラーメン店の入る建物がある。その他、大きな倉庫群は昔のままである。その中心が丹頂蔵という名前で、祭りでは一帯を開放し、駐車広場でアトラクションなどが行われる。昼過ぎに会場に行くと、結構なにぎわいである。
札幌唯一の蔵元の地酒をいろいろ味わい、仕込み水も楽しむ。広場ではメーンイベントのジョー山中さんのショーだ。歌がうまい。圧倒的に秀でている。プロとアマの差というのは生歌を聞くと、歴然としたものがある。おなじみの映画「人間の証明」の主題歌やスタンダードの数々をたっぷりと聞かせてくれる。お酒によく合う。
気分よく飲んでいると、路上アート付近に見たことのある人影がある。しばらく見ていて、「あっ」と思った。札幌在住の作家のM・Hさんである。北海道新聞文学賞を取り、作品も映画化されているユニークな恋愛作家だ。
Mさんは不思議な魅力がある人で、ご主人にも初めて会い、3人でのんびり日なたぼっこをしながら、昼酒を楽しんだ。まったりとした気分が気に入ったのか、トンボもやってきて1時間ほど私のジャンパーの上でひと休みして行った。
たいした話もしなかったが、何事も技量が優れているということと、オーラを持続することは難しいということで、一致した。確かに、「うまい」「できる」からといって、その人がいつも評価されるとは限らない。若さや時流というものが影響することもある。五臓にしみわたる酒に酔わされながら、心が少し痛んだ。
(東京五輪から30年余、感激を再びの声聞こえる体育の日に)
【いまさら探検隊】★★★
<14>「二条市場」=札幌市中央区南2東1、2

私は二条市場裏に住んでいる。もう22年ほど前に建てられたマンションの一室がわが家である。当時は倉庫跡に生まれた大きなマンションで、近隣住民には迷惑だったかもしれない。しかしながら、近年は大型マンション建設ラッシュで、古びたマンションはさほど目立たなくなった。新しいマンションが次々に建って、なじんだ風景が変わってくると目障りに思うのだから、エゴイズムというか人間のものの感じ方とは自分勝手である。
さて、二条市場だ。昔は「二条魚町」と言うほうが一般的で、「魚町」の名を付けた薬局もあった。最近は普通に二条市場という人がほとんどである。魚介類のほかに野菜果物も扱っており、もともと市民の台所であったが、有名になるに連れて観光名所となり全国からのお客さんが相手だ。
札幌市中央区役所のホームページにある「歴史の散歩道」によれば
「この市場が生まれたきっかけは、明治初期に石狩浜の漁師が石狩川を上って札幌に入り、鮮魚を売り始めたことといわれています。初めは、創成川を行き交う搬送船の荷の積み下ろしをする人たちを相手に商売をしていました。当時は、商店の数が十三軒であったことから、「十三組合」と呼ばれたそうです。
こうして自然に発生した市に転機が訪れ、現在のような魚市場が形作られたのは、明治三十六年(一九〇三年)。その前年の大火事で、ここ一帯が焼失しましたが、苦労の末、魚市場があらためて建設されると、以前にも増してにぎわうようになりました。」
とある。なるほど。創成川が交通路として役立っていたことが、市場の発生につながっていたわけだ。現在、創成川は工事の真っ最中で、昔日の面影は全くなし。以前も書いたことであるが、残念至極である。
市場の売り物の目玉と言えば、カニとサケであろう。でっかいタラバガニや秋アジが並ぶと、自分では買わないまでも、なんだか豊かな気分になる。観光客も珍しそうに眺めている。活気という意味では、かつてのような「二条市場=オンリーワン」的な色彩は薄れたので、現在は独自色の工夫が一層迫られているようだ。
裏小路には飲食店が並ぶ。こちらは市場の関係者が来るのか朝早くから店を開き、午後には佳境に入っているのが面白い。昼からカラオケを聞けるというのも、ここら辺の特色か。最近は若い人向きのカレー店やイタリア料理の店もあり、それが結構流行っているという。時代の流れか、おじさんの聖域も少しずつ崩れてきている。(2005.10.10)
<さよならだけが、人生じゃないぞ>
スリリングなクラシック・コンサートだった。10月7日に札幌コンサートホール・キタラで開かれた「グレート・マスターズ」公演である。それというのも古典は苦手な谷口である。失礼ながら、いつもは遠慮したいクラシックなのに、(だって、ブラボーって真顔で叫ぶのになじめない! じゃない)、今回は舞台に釘付けになった。
「グレート・マスターズ」というのは日本のクラシック音楽界の草創期から現在まで、発展を支えてきた大ベテランの公演だ。2002年に東京で初めて開かれ、4年目の今回は東京以外で初めて開催地に札幌が選ばれた。出演は中沢桂氏(ソプラノ)栗林義信氏(バリトン)らで、札幌では北海道二期会の発展に尽力した池上恵三氏(バス・バリトン)と、国際的ピアニスト遠藤郁子氏の母でもある遠藤道子氏(ピアノ)も加わった。
出演者の最年少65歳、最高齢は94歳という顔ぶれ。ちなみに、遠藤道子さんは88歳だそうだ。そんなわけで、出演者がもし倒れたら…、演奏が止まってしまったら…。そんなハラハラ感を覚えながらで見ていた。司会者の方も高齢で、オフビートMCだ。
だが、失礼な不安は途中で変わった。90を過ぎてもなおシューベルトの弦楽四重奏を弾き、バッハの組曲に挑む姿を見ていると、不思議な感動が沸き上がってきた。人間は凄いな。人間の肉体に刻み込まれた修練と精神の力を垣間見るのだ。いつ倒れたっていい。全力を尽くす姿は美しく、心に響いた。
コンピューターの将棋は、人間を上回る演算能力を多くの場面で発揮するそうだ。音楽だって、譜面を読ませていけばコンピューターのほうが正確な演奏をしそうだ。だが、それでも人間が将棋を指して、人間がピアノを弾いたほうがおもしろい。技術では解消しないものがある。それを精神の至上性というと曖昧すぎるけれど。
閑話休題。「いまさら探検隊」13で「なんもさストーブ」を取り上げた。その中で<「なんもさ」って言うのは、「そんなことはどうってことないよ」という意味の北海道弁だ。僕の先輩にもお酒を飲んで酔っ払うと、「谷口君、なんもだ」と言うのが口癖の困った人がいた。実は本人にはなんでもないことなのだが、私にとっては結構迷惑だなんてこともあったものだ>と書いた。
実はその「なんもさ先輩」が先日、急性心不全で急逝した。ウオーキングの途中で、異常を訴え、多くの関係者による懸命の手当のかいなく不帰の身となったのだ。享年59。最近は行きつけの酒店でも姿を見かけることが少なかった。「会わないね」と女将と話すこともあったのだが、唐突にさよならだけがやってきた。
90歳でも59歳でも人間の一生は変わらない。とはいえ、59歳は早い。なぜなら、それは我が身にジンと響くからだ。死が他人事じゃないということだ。これからは前進的な楽天主義で行きたい。いつ死んでも悔いのないように、頑張って生きねばと思う。
(神なき月の人の世は煩わしき事ばかり)
【いまさら探検隊】★★★
<15>「北大構内&クラーク像」=札幌市北区
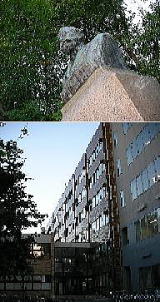
ひょんなことから、北大に「地域ジャーナリズム論」の講義に出かけている。私の担当は10月中の3回である。出席者は中国からの研究生を含め10人足らず。こぢんまりとしたゼミである。それぞれの問題意識のレベルがバラバラなので、どこまで地域に密着した報道の話をできるか、いささか難しい。
大学を出てから30数年。実質的には初めて学舎の中に入った。小さな昂ぶりと緊張と感慨を覚えた。アカデミズムとは無縁、権威主義とは決別の道を選んできたので、講師として大学に戻っている自分に対して、なんだか時間が経つことの皮肉を感じたのだ。
構内は建築バブルである。広かったキャンパスの中はどこもかしこも建物だらけである。お上の施設はカネの使い方が違うものだと、恐れ入らされる。昔の教養部のあたりは、なんともみっともなくなっている。文学部は、と見ると、どでかい建物が前方に鎮座して見る影もない。かつて軍艦講堂と言っていた荒々しい建物は探しても見つからなかった。ましてや、文連会館やら解放会館など、あろう筈もない。
そんな構内で、変わらぬたたずまいを見せるのは、クラーク博士の像である。北大には5つのクラーク像があるらしいが、一般的なのは中央ローンにある胸像である。近年は羊ヶ丘方面にある指差し全体像のほうが有名であるが、北大構内のそれこそ伝統もあり懐かしい。もっとも僕らの学生時代はペンキを塗られたり、結構悲惨なこともあったが…。
「ボーイズ ビー アンビシャス」。青年よ(少年よ)大志を抱け。クラーク博士が短い北大滞在を終えて、札幌郊外で別れる時に、若者たちに残したとされる名言。これにまつわるエピソードも多いが、確かに良い言葉だ。若者が夢を持たなくなったら、その世界は可能性を閉ざしたということだ。もっとも、最近の私のスローガンはこうだけど。
「オールド ボーイズ ビー アンビシャス !」(2005.10.14)
<言うは易く行うは難し>
旭川時代に何度か文章寄稿を依頼されたことがある。最初はエッセーのつもりだったが、それじゃなんだかつならないので、結局、ショートストーリーを書いた。小説のようなものである。たとえば、次のような作品である。
<魔法の時計>
「君は時間にルーズだ。管理職失格だぞ」
会社に着く早々、社長の雷が落ちた。私は「すいません」と謝ったが、悔しさでいっぱいだった。
「叱られたのかい」
買物公園でだれかの声がした。目をやると、見慣れぬ露店があった。店主はパンダのような顔をしている。
「十五分遅れただけで、怒られまして」と私。
「それは可哀想に。この魔法の時計をあげる。これをつければ、もう時間に遅れることはないよ」
「本当ですか。信じますよ、ありがとう」
私は藁にもすがる思いで、時計に手を伸ばした。お金を払おうとしたが、魔法使いのパンダは受け取らない。「使い方だけは間違えないでよ」と厳しく言った。
その時計は、長針と短針、それに秒針だけのシンプルなデザインだ。
私は「午後八時に帰宅するぞ」と、時計を見ながら思った。だが、いつもの癖で雑貨屋や古着屋などを冷やかしてしまった。時計を見たときは七時だったので、家に着いたのはとうに九時を過ぎているはずだった。
ところが、である。時計を見ると、ぴったり午後八時だった。不思議なことがあるものだ。
それからはすべての行動が時間どおりになった。時計を見て「正午までに仕事を終わるぞ」と思うと、どんなにたくさんの作業があってもきれいに片付く。「午後七時の汽車に乗る」「午後八時の音楽会」etc.。
なんでもジャスト・オン・タイムだ。
それならば、と私の中に怠惰の虫がうごめきだした。思いっきり寝てから、昼ごろに会社に行くことにしたのである。どんなに遅くても朝帰りでも、十二時間くらいは熟睡する。それでも「午前九時出社」と時計に念じれば、ちょうど午前九時に会社に着くのである。
社長は「偉いぞ。最近は遅刻しないな」と呆れ顔半分で誉めてくれる。ふふふ、いい気分だ。
そのうち、私は会社に行かなくなった。
「私が行くまで、どうせ午前九時は来ないんだから」
私は何日もぐうたらで過ごした。幾日たったかも忘れたころ、そろそろ会社に行ってやろうかと思った。
「九時に会社」。そう念じて家を出た。だが、いつまで経っても会社に着かないのだ。歩いても歩いても着かない。ついに苦しくて泡を吹いて倒れた。欲望の赴くまま使い方を間違えたから、天罰が落ちたに違いない!
自分を悔いながら、かすむ眼で時計を見た。バンドに「使用上の注意」の小さい文字。くそっ!
「電池が切れれば止まります。 魔法の時計」 <おわり>
最初は一回のつもりだったが、これが意外に好評だった。ついつい転勤まで1年ほど書いてしまった。だが、厳しい目利きの読者からは「まだまだ物足りないぞ」と叱られた。本人はいい気でも素人芸とはそんなものである。
私もこのホームページで「きょうの本」などという読書感想文を書いている。偉そうなことを言っているが、作家は「文句があるなら、あんたにどれほどのものができるのよ」と思っているに違いないのだ。で、実際に書いてみると、小説は難しい! 頭の中で考えているようには書けないものだ。なぜだろうと思うが、やはり修行不足ということか。
年を取ることで、ますますそのことを実感する。何事も実践するのは大変なことだ。頭ではできるように思っていても、なかなかできない。批判はできても実践は難しい。まさに「言うは易く、行うは難し」である。それでも、向上心と努力だけは失わないようにしたいと思うのであるが…。
(そうか、10月21日は「国際反戦デー」だったのか、と驚く今日この頃)
【いまさら探検隊】★
<16>「小樽運河」=小樽港周辺

何年かぶりで訪れた小樽運河には観光客があふれていた。なぜか人力車が行き交い、もう観光地では珍しくない中国語もあちこちで飛び交っている。運河の水は相変わらず緑濃く、景観の美しさだけがひどく印象的だった。だれの言葉だったかはっきり覚えていないが、死ねば死にきり、死は水際だっている、というような一節が頭をよぎった。
小樽のことを思うと、さまざまな思いがよぎる。1974年に僕は初めての勤務先であるこの町に着任した。文学について考える出発点にある伊藤整の育った町。僕は学生時代に塩谷のゴロダの丘を訪ねているし、整の通った高商への道や花園界隈を歩いたものだ。そして、とても魅力的な女性が住んでいたこともあった。
最初の仕事で僕はあくせくしていた。今もそうだが、自分に自信が持てず、先輩にしごかれていたのだ。花園の飲食店街も僕にはなじめなかった。だから、今でも新人記者などで仕事のできない人を見ると、彼には絶望しなければいつか自分のチャンスは来るのだということを信じていてほしいと思う。苦しくても潮目が変わるときはある。そのチャンスをつかまえられるかどうか。可能性のない人間なんていないのだ。
小樽運河は、新人記者の僕には雪で倉庫が崩れたり、人が落ちたりする程度の事件現場だった。絵を描いている人もいたが、想像力を失いそうで嫌だった。そうこうして臨港道路建設に伴う運河の保存論争が起こった。僕は坂口安吾の日本文化論や堕落論の影響を受けていたと言っておこう。わかる人には僕の考えがわかっていただけると思うが、考古学の世界ではなく人間の営みこそ僕の価値論の基本であった。
啄木は小樽の街の活気を「声の荒さ」と表現した。そのことは小樽の人には必ずしもプラスとして受け止められなかった。だが、僕は小樽運河もそのような啄木の視点において評価されるべきだと今でも信じている。そして我が伊藤整は屈折した人だった。日本の近代の歪みを真正面から見据え、老獪に批判した人だった。彼が生きていれば、どんなことを言うだろうかと思った。こんなふうに僕は相も変わらず自信なげに訳のわからんことを書いているが、五感の形成は世界史の労作であり、大切なものは目に見えないものだ。(2005.10.20)
【いまさら探検隊】★
<17>「丸井今井」=中央区南1西2界わい

昔むかし。道民から「さん」付けで呼ばれていた企業がありました。さて? それが丸井さんです。札幌の老舗と言えば、丸井さん。本店前を市電が走り、待ち合わせにもってこい、今でいうランドマークのような場所でした。
白老の田舎育ちの私は、苫小牧の鶴丸デパート、札幌の丸井デパートというと憧れでした。なにしろ、鶴丸では初めてエスカレーターに乗った記憶があります。うちのおやじはもう死んでしまいましたが、丸井さんから「とうまん」を買ってくるのが楽しみでした。(缶に入れて密かに舐めていたのが、金平糖でした)。その縁で、私は今も墓参りを兼ねて母親が一人で住む実家に行くときは、キオスクで「とうまん」を買って帰るほどです。東京に行って駅前の赤いカードの「丸井」を知りましたが、そのグレードから言えば、札幌の丸井さんのほうがはるかに上ですね。
その丸井さん。バブル時代の事業拡張が裏目に出て、経営がおかしくなりました。それで、経営も大手と連携するなど変わりつつあります。このため苫小牧と小樽の支店は10月23日で閉店してしまいました。多くの惜しむ声が聞かれたのは、地域に親しまれてきた証拠でしょう。
私は丸井ファンですから、閉店セールをやっている両店に行って来ました。苫小牧ではポーチとハンカチセットを買い、小樽では下着やワイシャツを買ってきました。なかなかお値打ち品が多いのでセールは大盛況でしたが、店の雰囲気がなんとなく暗いのが、ふだんは客足が伸びなかった理由かもしれません。
札幌は丸井さんの本拠地です。大通と南1条界隈は丸井さんだらけです。交差点から見ると、壮観です。先日、大通館に行ったのですが、女性向きの館のようで、私には入りずらかった印象です。ブランド志向とバタ臭さと、オンリーワンとナンバーワンと、なんかもっと個性化してくれるといいなと思っています、そのためには試行錯誤が必要です、頑張ってほしいと思っています。(2005.10.28)
【いまさら探検隊】★
<18>「北海道赤十字血液センター」=西区山の手2の2

自慢じゃないが、注射嫌いです。看護師さんは好きですが、それでも注射器を持って「痛くないですよ、力を抜いて目を開けて」と言われると、ますます硬直してしまう私です。で、チクリ。やっぱ、痛い!じゃないですか! 私は血管が細いので、なかなか良い打ちどころが見つからない。それで、血管を浮き出させようとたたかれたり腕を替えたり。あれで、ますます恐怖感は募ります。子どもの気持ちがよくわかります。
閑話休題。かくいう私でも、一度だけ献血をしたことがあります。もうだいぶ前で時期は忘れましたが、地下街の大通出張所で200CC献血し、ジュースをもらいました。そんな気持ちになったのは、珍しく血液が足りないというキャンペーンをやっていたか、よほど良い人間になっていたのに違いありません。でも、献血すると安心感もあるし、いろいろな意味で、良かったなあ、と思います。
先日、仕事の関係で、献血の総本山ともいうべき北海道赤十字血液センターに行ってきました。大通や札幌駅前などの出先はなじみがありますが、ビルは立派です。でも、ちょっと幹線路から奥まっていて、近隣はともかく遠方の人間には不便な印象です。
同センターの資料によると、道内には札幌以外には旭川、釧路、室蘭、函館に血液センタ−があるようです。全道で、年間約32万人の献血者がいますが、札幌の北海道血液センターの扱い分は約16万人で、半分はこちらが窓口になっているようです。ちなみに、全国では540万人の献血者数ですので、全体の6%。人口の比率に比較的近い関係にあるようです。このコラムを書いている時に、献血者の約1%に健康被害が出ているとの記事もありました。慎重な作業を望みたいところです。
父親は心臓手術中に亡くなりました。訴訟にすると面倒なので、結局、医療ミスにはしませんでしたが、ひどいものでした。心臓の裏に傷を付けて血が止まらなくなったというのです。緊急輸血が必要になりました。ですが、父はAB型で、私はA型なのです。結局、会社の同僚・後輩のみなさんの協力を得ましたが、助かりませんでした。献血の大切さを思いました。(2005.11.04)
<超高齢社会は価値観の転換が必要だ>
超高齢社会である。私はまだ50代であるが、近親者は60代、70代、80代で、本当に年寄りばかりである。子どもがいないことは別段、寂しくはないが、若い世代の声が身近で聞けないのは精神衛生的にはよろしくない。高齢者の場合は健康のことやらだれかれがどうしたのと、どうしても話題が内向きになってしまうからである。90いくつかで亡くなった本家筋の隣のおばあさんは「年寄りの話は聞きたくない。若い者がいい」と、孫やひ孫たちとの新鮮な会話を楽しんでいたものだ。
新聞では編集委員が中心になった連載「子どもがいなくなる−北海道あすの課題 第一部」もスタートした(第1部は11日で終了)。全国を上回るハイペースで進む少子・高齢化に見舞われている北海道の近未来がどうなるのか。データで裏づけを取りながら、課題を探ろうという意欲作である。子どもが生まれなくなると、学校は消えていき、教育環境が低下するのみならず、地域の疲弊が進むことは明らかだ。だが、一方で子どもを産みたくない人や産めない社会事情もある。意識の変化は制度をいじるだけでは簡単には戻らないのである。
私たちの親世代では10人前後のきょうだいが普通だった。私たちになると3人前後となり、私たちの子の世代では1人前後という感じだ。少子化により兄弟げんかが消え、子ども社会の経験の継承もなくなる。一方で、親子の確執は増すだろう。経済生活レベルでの豊かさが増したことは間違いないが、社会の豊かさはずいぶん失われた。
独り暮らしの実母は公的介護が頼りである。独り暮らしに近い義母は84歳なので介護認定を受けたのを機に、ヘルパーさんに週2回来てもらうよう手続きをした。そのためには膨大な契約書類があって、とても老人が1人で書けるものではないので、代理人として私が判を押した。母の世代は私たちがいるからいいが、私たちには子どもがいないので、自分でなんとかしなければならない。
先日、「未使用の火葬場 焼却炉に2遺体 福井・夫婦心中か」(11月9日朝刊)という記事が載っていた。それによると、福井県大野市七板の使用されていない火葬場の焼却炉で白骨化した2遺体が見つかった。2人は80歳の夫と82歳の妻で、心中を図ったものらしい。自宅からは「妻とともに逝く」と書いた夫の日記が見つかったからだ。2人はまきで火をおこした焼却炉に一緒に入り、中から扉を閉めて焼身自殺したとみられる。近所の住民によると、妻は寝たきりの状態で、夫が看病をしていたが、最近は体調を崩していたという。
涙なしには読めない記事だった。他人事ではないと多くの人が感じただろうと思う。高齢社会の話になると、やはり内向きになってしまう。老人力という言葉が流行ったが、ああいう、あっけらかんとした楽天性を大切にしたい。同じように、パラダイム・チェンジという言葉も流行ったが、ものの見方、社会のあり方を変えなくてはならない。その主役はまさに高齢世代となる団塊の世代であり、私たちに託された課題でもある。
(「朝は4本、昼は2本、夜は3本足の生き物は」というなぞなぞありましたね)
【いまさら探検隊】★★☆
<19>「北海道神宮頓宮」=中央区南2東3

札幌の古書籍商組合が定期的に開くセリ市が、中央区南2東3の屯宮神社で毎月第3水曜日に開かれているそうだ。神社で古書の入札をしているとはまことに意外である。しかも、屯宮神社はわが家のご町内である。その身近な場所が知の宝庫になっていることに驚いた。そこでは9月には秋祭りもあり、創成川東岸エリアに住む子ども(いや善男善女というべきか)には小さいながらも地域に密着している場所なのである。
屯宮神社は北海道神宮頓宮というのが一般的だ。札幌っ子にとっては欠かすことのできない初夏の一大イベント「札幌まつり」(北海道神宮例祭)で、市内を練り歩くみこしがひと休みする場所だ。北海道神宮のHPを見ると、「明治11年6月15日の例祭には、札幌中教院・神道事務局(現在の北海道神宮頓宮=中央区南2条東3丁目)開設の神事が斎行され、札幌神社の祭神と中教院の四神の神霊をそれぞれに招き、神輿一基が市街地をご巡幸した。これが渡御(とぎょ)の始まりです」とある。まさに、頓宮なくして札幌まつりはあり得ないのである。
私はわが家から自転車でサッポロファクトリーに行く途中に神社の前を通る。11月は酉(とり)の市で、それを伝えるのぼり旗も、この季節には立っている。別にお祓いをしてもらっているわけではないので、通り過ぎるだけではなんのご利益もない。それでも、寺社というものは仏教、神道、キリスト教を問わず、本来は神の依り代でありながら、昔から市が立ったり、とても人間くさい場所であると思う。(2005.11.11)
【いまさら探検隊】★
<20>「本陣狸大明神社」=中央区南2条西5丁目

札幌の商店街と言えば、アーケードのある狸小路が老舗です。私は休日になると、創成川の下をくぐって1丁目から6丁目あたりをうろちょろしています。雨の日は会社に行く時は少し遠回りになりますが、狸小路を歩きます。そんな大好きな狸小路ですが、商店街としては130年を超える歴史を持つのだそうですから、すごいですね。
「さっぽろ文庫」の第36巻が「狸小路」特集です。同書によれば、狸小路のルーツは明治4年(1871年)に開拓使本庁が札幌に移り、南1条から3条までの街並みが形成されたのが始まりだそうです。もっとも、かわいらしい愛称は別のようです。薄野がお上公認の遊郭街であったのに対して、隣接して非公認のエリアができた。白首のきれいな女性たちが出没し、それが人をはやして楽しませるが、ちょっと尻尾も出す狸に擬され、そのあだ名がそのまま本名となり、狸小路となったそうです。
明治の狸小路の3大キーワードは「白首屋」「寄席」「勧工場」とのこと。今風に言えば、セックス&エンターテインメント&ショッピングでしょうか。とりわけ、勧工場はデパートやスーパーマーケットの先駆けのようなものですから、そりゃあ魅力的だったと思われます。楽しそうだなあ。ちょっと、いかがわしいけれど、わくわくするというのが狸小路なのです。いいじゃないですか。
ちなみに「わたしゃ さっぽろね 狸小路の 生まれよ 色が黒いが 情がある」なんて「狸小路ばやし」(昭和29年、ほしはまさくら作詞)もあったそうです。今は、「ぽんぽこサンバ」のほうが有名ですが。これは余談ですね。
どの街にも栄枯盛衰があります。大型店の札幌進出に攻められましたし、最近は郊外のショッピングセンターや札幌駅前ゾーンが商業地として興隆しています。狸小路は何度目かの正念場を迎えているかもしれません。でも、セックス(これは広い意味ですよ、念のため)&エンターテインメント&ショッピングの3大キーワードをうまく展開するともっと可能性があると思います。
狸小路5丁目には、シンボルの狸をまつった神社があります。能書きによると、「大福帳をなぜると商売繁盛」「お腹をなぜると安産」とか狸の8徳があるそうです。本当かどうかわかりません。狸ですから、案外、だますことがあるかもしれませんし。開運おみくじもありますが、どうなんでしょう。近隣にはパチンコ店が増えましたが、私の場合、あまりご利益は顕著ではありませんね。それもご愛嬌だと思っています。(2005.11.18)
【いまさら探検隊】★
<21>「北海道庁 赤れんが庁舎」=中央区北3西6

私は大きいものが苦手であります。国家権力とか、グーンと落ちて北海道庁。なんだかなあ、ですが。官僚制というものは、人間に対して優しくありません。その制度が欲しているのは秩序と効率ですからね。逸脱とか越境性を魅力的に感じてきた私のような一庶民としてはありがたすぎて近寄りたくない。でもね、木陰ができ池があったりしていると、いいなあ、と思ってしまうです。とりわけ、観光スポットの「赤れんが庁舎」。レトロです。落ち着きますから、困ってしまいますよね。
さて、その赤れんが。ものの本によると、米国マサチューセッツ州議事堂をモデルにして明治21年(1888年)にアメリカ風のネオ・バロック様式で建てられたとのこと。明治期を代表する建物なのだそうです。庁舎北側には「開拓使本庁舎跡」の石碑もあるようです。道庁の本庁舎として使われていましたが、今は北海道立文書館などとして使われています。
そんな由緒ある建物ですから、札幌駅前通りから大通りへ北3条の角を右に折れると銀杏並木が続いています。なんでも、これは本道初の並木。その道路は初の舗装道路であるそうです。確かに、なかなか趣きがあります。車も公園のような道庁にぶつかりますので、直進できず左折して大通方向に抜けねばなりません。
池には野鳥が遊び、立派な彫刻も並んでいます。ぜいたくです。一般市民や観光客もブラブラ歩くことができますが、役所の一部ですから、個人的には今ひとつ落ち着きませんね。隣に現在の道庁の建物(結構古いですが)があって、業者やら手続きの道民が慌しく行き交いますし、近くには北海道警察もあります。世俗のセコセコ(コセコセ?)感が、赤れんが庁舎の風格に似合いません。「泥中の蓮」とか「掃き溜めの鶴」とか、いろいろな言い方がありますが、やはりいいものはそれなりの場所にあったほうがいいですね。
(2005.11.25)
■トップページに戻る
秋来ぬと目にはさやかに見えねども。風に吹かれて、ぶらりと外に出る。時は10月2日の日曜日。自宅から近くにある日本清酒の工場前に行くと、「丹頂蔵祭り」をやっていた。ここは「千歳鶴」という銘柄で親しまれている老舗。私が以前いた旭川にある名門・高砂酒造を実質的に買った酒屋でもある。
もう10数年前に前になる。中古の自動車を持っていたものの、駐車場のない私は日本清酒の工場敷地の駐車場を月1万2000円と消費税360円で借りていたのである。街中ではほどほどの値段であり、便利に使わせてもらった。いわば私にとっては車の大家さんが千歳鶴なので、いささか懐かしい。
殺風景だったスペースには酒ミュージアムという宣伝用の施設が建ち、向かいにはミュージアム・アネックスというラーメン店の入る建物がある。その他、大きな倉庫群は昔のままである。その中心が丹頂蔵という名前で、祭りでは一帯を開放し、駐車広場でアトラクションなどが行われる。昼過ぎに会場に行くと、結構なにぎわいである。
札幌唯一の蔵元の地酒をいろいろ味わい、仕込み水も楽しむ。広場ではメーンイベントのジョー山中さんのショーだ。歌がうまい。圧倒的に秀でている。プロとアマの差というのは生歌を聞くと、歴然としたものがある。おなじみの映画「人間の証明」の主題歌やスタンダードの数々をたっぷりと聞かせてくれる。お酒によく合う。
気分よく飲んでいると、路上アート付近に見たことのある人影がある。しばらく見ていて、「あっ」と思った。札幌在住の作家のM・Hさんである。北海道新聞文学賞を取り、作品も映画化されているユニークな恋愛作家だ。
Mさんは不思議な魅力がある人で、ご主人にも初めて会い、3人でのんびり日なたぼっこをしながら、昼酒を楽しんだ。まったりとした気分が気に入ったのか、トンボもやってきて1時間ほど私のジャンパーの上でひと休みして行った。
たいした話もしなかったが、何事も技量が優れているということと、オーラを持続することは難しいということで、一致した。確かに、「うまい」「できる」からといって、その人がいつも評価されるとは限らない。若さや時流というものが影響することもある。五臓にしみわたる酒に酔わされながら、心が少し痛んだ。
(東京五輪から30年余、感激を再びの声聞こえる体育の日に)
【いまさら探検隊】★★★
<14>「二条市場」=札幌市中央区南2東1、2

私は二条市場裏に住んでいる。もう22年ほど前に建てられたマンションの一室がわが家である。当時は倉庫跡に生まれた大きなマンションで、近隣住民には迷惑だったかもしれない。しかしながら、近年は大型マンション建設ラッシュで、古びたマンションはさほど目立たなくなった。新しいマンションが次々に建って、なじんだ風景が変わってくると目障りに思うのだから、エゴイズムというか人間のものの感じ方とは自分勝手である。
さて、二条市場だ。昔は「二条魚町」と言うほうが一般的で、「魚町」の名を付けた薬局もあった。最近は普通に二条市場という人がほとんどである。魚介類のほかに野菜果物も扱っており、もともと市民の台所であったが、有名になるに連れて観光名所となり全国からのお客さんが相手だ。
札幌市中央区役所のホームページにある「歴史の散歩道」によれば
「この市場が生まれたきっかけは、明治初期に石狩浜の漁師が石狩川を上って札幌に入り、鮮魚を売り始めたことといわれています。初めは、創成川を行き交う搬送船の荷の積み下ろしをする人たちを相手に商売をしていました。当時は、商店の数が十三軒であったことから、「十三組合」と呼ばれたそうです。
こうして自然に発生した市に転機が訪れ、現在のような魚市場が形作られたのは、明治三十六年(一九〇三年)。その前年の大火事で、ここ一帯が焼失しましたが、苦労の末、魚市場があらためて建設されると、以前にも増してにぎわうようになりました。」
とある。なるほど。創成川が交通路として役立っていたことが、市場の発生につながっていたわけだ。現在、創成川は工事の真っ最中で、昔日の面影は全くなし。以前も書いたことであるが、残念至極である。
市場の売り物の目玉と言えば、カニとサケであろう。でっかいタラバガニや秋アジが並ぶと、自分では買わないまでも、なんだか豊かな気分になる。観光客も珍しそうに眺めている。活気という意味では、かつてのような「二条市場=オンリーワン」的な色彩は薄れたので、現在は独自色の工夫が一層迫られているようだ。
裏小路には飲食店が並ぶ。こちらは市場の関係者が来るのか朝早くから店を開き、午後には佳境に入っているのが面白い。昼からカラオケを聞けるというのも、ここら辺の特色か。最近は若い人向きのカレー店やイタリア料理の店もあり、それが結構流行っているという。時代の流れか、おじさんの聖域も少しずつ崩れてきている。(2005.10.10)
<さよならだけが、人生じゃないぞ>
スリリングなクラシック・コンサートだった。10月7日に札幌コンサートホール・キタラで開かれた「グレート・マスターズ」公演である。それというのも古典は苦手な谷口である。失礼ながら、いつもは遠慮したいクラシックなのに、(だって、ブラボーって真顔で叫ぶのになじめない! じゃない)、今回は舞台に釘付けになった。
「グレート・マスターズ」というのは日本のクラシック音楽界の草創期から現在まで、発展を支えてきた大ベテランの公演だ。2002年に東京で初めて開かれ、4年目の今回は東京以外で初めて開催地に札幌が選ばれた。出演は中沢桂氏(ソプラノ)栗林義信氏(バリトン)らで、札幌では北海道二期会の発展に尽力した池上恵三氏(バス・バリトン)と、国際的ピアニスト遠藤郁子氏の母でもある遠藤道子氏(ピアノ)も加わった。
出演者の最年少65歳、最高齢は94歳という顔ぶれ。ちなみに、遠藤道子さんは88歳だそうだ。そんなわけで、出演者がもし倒れたら…、演奏が止まってしまったら…。そんなハラハラ感を覚えながらで見ていた。司会者の方も高齢で、オフビートMCだ。
だが、失礼な不安は途中で変わった。90を過ぎてもなおシューベルトの弦楽四重奏を弾き、バッハの組曲に挑む姿を見ていると、不思議な感動が沸き上がってきた。人間は凄いな。人間の肉体に刻み込まれた修練と精神の力を垣間見るのだ。いつ倒れたっていい。全力を尽くす姿は美しく、心に響いた。
コンピューターの将棋は、人間を上回る演算能力を多くの場面で発揮するそうだ。音楽だって、譜面を読ませていけばコンピューターのほうが正確な演奏をしそうだ。だが、それでも人間が将棋を指して、人間がピアノを弾いたほうがおもしろい。技術では解消しないものがある。それを精神の至上性というと曖昧すぎるけれど。
閑話休題。「いまさら探検隊」13で「なんもさストーブ」を取り上げた。その中で<「なんもさ」って言うのは、「そんなことはどうってことないよ」という意味の北海道弁だ。僕の先輩にもお酒を飲んで酔っ払うと、「谷口君、なんもだ」と言うのが口癖の困った人がいた。実は本人にはなんでもないことなのだが、私にとっては結構迷惑だなんてこともあったものだ>と書いた。
実はその「なんもさ先輩」が先日、急性心不全で急逝した。ウオーキングの途中で、異常を訴え、多くの関係者による懸命の手当のかいなく不帰の身となったのだ。享年59。最近は行きつけの酒店でも姿を見かけることが少なかった。「会わないね」と女将と話すこともあったのだが、唐突にさよならだけがやってきた。
90歳でも59歳でも人間の一生は変わらない。とはいえ、59歳は早い。なぜなら、それは我が身にジンと響くからだ。死が他人事じゃないということだ。これからは前進的な楽天主義で行きたい。いつ死んでも悔いのないように、頑張って生きねばと思う。
(神なき月の人の世は煩わしき事ばかり)
【いまさら探検隊】★★★
<15>「北大構内&クラーク像」=札幌市北区
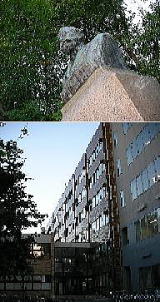
ひょんなことから、北大に「地域ジャーナリズム論」の講義に出かけている。私の担当は10月中の3回である。出席者は中国からの研究生を含め10人足らず。こぢんまりとしたゼミである。それぞれの問題意識のレベルがバラバラなので、どこまで地域に密着した報道の話をできるか、いささか難しい。
大学を出てから30数年。実質的には初めて学舎の中に入った。小さな昂ぶりと緊張と感慨を覚えた。アカデミズムとは無縁、権威主義とは決別の道を選んできたので、講師として大学に戻っている自分に対して、なんだか時間が経つことの皮肉を感じたのだ。
構内は建築バブルである。広かったキャンパスの中はどこもかしこも建物だらけである。お上の施設はカネの使い方が違うものだと、恐れ入らされる。昔の教養部のあたりは、なんともみっともなくなっている。文学部は、と見ると、どでかい建物が前方に鎮座して見る影もない。かつて軍艦講堂と言っていた荒々しい建物は探しても見つからなかった。ましてや、文連会館やら解放会館など、あろう筈もない。
そんな構内で、変わらぬたたずまいを見せるのは、クラーク博士の像である。北大には5つのクラーク像があるらしいが、一般的なのは中央ローンにある胸像である。近年は羊ヶ丘方面にある指差し全体像のほうが有名であるが、北大構内のそれこそ伝統もあり懐かしい。もっとも僕らの学生時代はペンキを塗られたり、結構悲惨なこともあったが…。
「ボーイズ ビー アンビシャス」。青年よ(少年よ)大志を抱け。クラーク博士が短い北大滞在を終えて、札幌郊外で別れる時に、若者たちに残したとされる名言。これにまつわるエピソードも多いが、確かに良い言葉だ。若者が夢を持たなくなったら、その世界は可能性を閉ざしたということだ。もっとも、最近の私のスローガンはこうだけど。
「オールド ボーイズ ビー アンビシャス !」(2005.10.14)
<言うは易く行うは難し>
旭川時代に何度か文章寄稿を依頼されたことがある。最初はエッセーのつもりだったが、それじゃなんだかつならないので、結局、ショートストーリーを書いた。小説のようなものである。たとえば、次のような作品である。
<魔法の時計>
「君は時間にルーズだ。管理職失格だぞ」
会社に着く早々、社長の雷が落ちた。私は「すいません」と謝ったが、悔しさでいっぱいだった。
「叱られたのかい」
買物公園でだれかの声がした。目をやると、見慣れぬ露店があった。店主はパンダのような顔をしている。
「十五分遅れただけで、怒られまして」と私。
「それは可哀想に。この魔法の時計をあげる。これをつければ、もう時間に遅れることはないよ」
「本当ですか。信じますよ、ありがとう」
私は藁にもすがる思いで、時計に手を伸ばした。お金を払おうとしたが、魔法使いのパンダは受け取らない。「使い方だけは間違えないでよ」と厳しく言った。
その時計は、長針と短針、それに秒針だけのシンプルなデザインだ。
私は「午後八時に帰宅するぞ」と、時計を見ながら思った。だが、いつもの癖で雑貨屋や古着屋などを冷やかしてしまった。時計を見たときは七時だったので、家に着いたのはとうに九時を過ぎているはずだった。
ところが、である。時計を見ると、ぴったり午後八時だった。不思議なことがあるものだ。
それからはすべての行動が時間どおりになった。時計を見て「正午までに仕事を終わるぞ」と思うと、どんなにたくさんの作業があってもきれいに片付く。「午後七時の汽車に乗る」「午後八時の音楽会」etc.。
なんでもジャスト・オン・タイムだ。
それならば、と私の中に怠惰の虫がうごめきだした。思いっきり寝てから、昼ごろに会社に行くことにしたのである。どんなに遅くても朝帰りでも、十二時間くらいは熟睡する。それでも「午前九時出社」と時計に念じれば、ちょうど午前九時に会社に着くのである。
社長は「偉いぞ。最近は遅刻しないな」と呆れ顔半分で誉めてくれる。ふふふ、いい気分だ。
そのうち、私は会社に行かなくなった。
「私が行くまで、どうせ午前九時は来ないんだから」
私は何日もぐうたらで過ごした。幾日たったかも忘れたころ、そろそろ会社に行ってやろうかと思った。
「九時に会社」。そう念じて家を出た。だが、いつまで経っても会社に着かないのだ。歩いても歩いても着かない。ついに苦しくて泡を吹いて倒れた。欲望の赴くまま使い方を間違えたから、天罰が落ちたに違いない!
自分を悔いながら、かすむ眼で時計を見た。バンドに「使用上の注意」の小さい文字。くそっ!
「電池が切れれば止まります。 魔法の時計」 <おわり>
最初は一回のつもりだったが、これが意外に好評だった。ついつい転勤まで1年ほど書いてしまった。だが、厳しい目利きの読者からは「まだまだ物足りないぞ」と叱られた。本人はいい気でも素人芸とはそんなものである。
私もこのホームページで「きょうの本」などという読書感想文を書いている。偉そうなことを言っているが、作家は「文句があるなら、あんたにどれほどのものができるのよ」と思っているに違いないのだ。で、実際に書いてみると、小説は難しい! 頭の中で考えているようには書けないものだ。なぜだろうと思うが、やはり修行不足ということか。
年を取ることで、ますますそのことを実感する。何事も実践するのは大変なことだ。頭ではできるように思っていても、なかなかできない。批判はできても実践は難しい。まさに「言うは易く、行うは難し」である。それでも、向上心と努力だけは失わないようにしたいと思うのであるが…。
(そうか、10月21日は「国際反戦デー」だったのか、と驚く今日この頃)
【いまさら探検隊】★
<16>「小樽運河」=小樽港周辺

何年かぶりで訪れた小樽運河には観光客があふれていた。なぜか人力車が行き交い、もう観光地では珍しくない中国語もあちこちで飛び交っている。運河の水は相変わらず緑濃く、景観の美しさだけがひどく印象的だった。だれの言葉だったかはっきり覚えていないが、死ねば死にきり、死は水際だっている、というような一節が頭をよぎった。
小樽のことを思うと、さまざまな思いがよぎる。1974年に僕は初めての勤務先であるこの町に着任した。文学について考える出発点にある伊藤整の育った町。僕は学生時代に塩谷のゴロダの丘を訪ねているし、整の通った高商への道や花園界隈を歩いたものだ。そして、とても魅力的な女性が住んでいたこともあった。
最初の仕事で僕はあくせくしていた。今もそうだが、自分に自信が持てず、先輩にしごかれていたのだ。花園の飲食店街も僕にはなじめなかった。だから、今でも新人記者などで仕事のできない人を見ると、彼には絶望しなければいつか自分のチャンスは来るのだということを信じていてほしいと思う。苦しくても潮目が変わるときはある。そのチャンスをつかまえられるかどうか。可能性のない人間なんていないのだ。
小樽運河は、新人記者の僕には雪で倉庫が崩れたり、人が落ちたりする程度の事件現場だった。絵を描いている人もいたが、想像力を失いそうで嫌だった。そうこうして臨港道路建設に伴う運河の保存論争が起こった。僕は坂口安吾の日本文化論や堕落論の影響を受けていたと言っておこう。わかる人には僕の考えがわかっていただけると思うが、考古学の世界ではなく人間の営みこそ僕の価値論の基本であった。
啄木は小樽の街の活気を「声の荒さ」と表現した。そのことは小樽の人には必ずしもプラスとして受け止められなかった。だが、僕は小樽運河もそのような啄木の視点において評価されるべきだと今でも信じている。そして我が伊藤整は屈折した人だった。日本の近代の歪みを真正面から見据え、老獪に批判した人だった。彼が生きていれば、どんなことを言うだろうかと思った。こんなふうに僕は相も変わらず自信なげに訳のわからんことを書いているが、五感の形成は世界史の労作であり、大切なものは目に見えないものだ。(2005.10.20)
【いまさら探検隊】★
<17>「丸井今井」=中央区南1西2界わい

昔むかし。道民から「さん」付けで呼ばれていた企業がありました。さて? それが丸井さんです。札幌の老舗と言えば、丸井さん。本店前を市電が走り、待ち合わせにもってこい、今でいうランドマークのような場所でした。
白老の田舎育ちの私は、苫小牧の鶴丸デパート、札幌の丸井デパートというと憧れでした。なにしろ、鶴丸では初めてエスカレーターに乗った記憶があります。うちのおやじはもう死んでしまいましたが、丸井さんから「とうまん」を買ってくるのが楽しみでした。(缶に入れて密かに舐めていたのが、金平糖でした)。その縁で、私は今も墓参りを兼ねて母親が一人で住む実家に行くときは、キオスクで「とうまん」を買って帰るほどです。東京に行って駅前の赤いカードの「丸井」を知りましたが、そのグレードから言えば、札幌の丸井さんのほうがはるかに上ですね。
その丸井さん。バブル時代の事業拡張が裏目に出て、経営がおかしくなりました。それで、経営も大手と連携するなど変わりつつあります。このため苫小牧と小樽の支店は10月23日で閉店してしまいました。多くの惜しむ声が聞かれたのは、地域に親しまれてきた証拠でしょう。
私は丸井ファンですから、閉店セールをやっている両店に行って来ました。苫小牧ではポーチとハンカチセットを買い、小樽では下着やワイシャツを買ってきました。なかなかお値打ち品が多いのでセールは大盛況でしたが、店の雰囲気がなんとなく暗いのが、ふだんは客足が伸びなかった理由かもしれません。
札幌は丸井さんの本拠地です。大通と南1条界隈は丸井さんだらけです。交差点から見ると、壮観です。先日、大通館に行ったのですが、女性向きの館のようで、私には入りずらかった印象です。ブランド志向とバタ臭さと、オンリーワンとナンバーワンと、なんかもっと個性化してくれるといいなと思っています、そのためには試行錯誤が必要です、頑張ってほしいと思っています。(2005.10.28)
【いまさら探検隊】★
<18>「北海道赤十字血液センター」=西区山の手2の2

自慢じゃないが、注射嫌いです。看護師さんは好きですが、それでも注射器を持って「痛くないですよ、力を抜いて目を開けて」と言われると、ますます硬直してしまう私です。で、チクリ。やっぱ、痛い!じゃないですか! 私は血管が細いので、なかなか良い打ちどころが見つからない。それで、血管を浮き出させようとたたかれたり腕を替えたり。あれで、ますます恐怖感は募ります。子どもの気持ちがよくわかります。
閑話休題。かくいう私でも、一度だけ献血をしたことがあります。もうだいぶ前で時期は忘れましたが、地下街の大通出張所で200CC献血し、ジュースをもらいました。そんな気持ちになったのは、珍しく血液が足りないというキャンペーンをやっていたか、よほど良い人間になっていたのに違いありません。でも、献血すると安心感もあるし、いろいろな意味で、良かったなあ、と思います。
先日、仕事の関係で、献血の総本山ともいうべき北海道赤十字血液センターに行ってきました。大通や札幌駅前などの出先はなじみがありますが、ビルは立派です。でも、ちょっと幹線路から奥まっていて、近隣はともかく遠方の人間には不便な印象です。
同センターの資料によると、道内には札幌以外には旭川、釧路、室蘭、函館に血液センタ−があるようです。全道で、年間約32万人の献血者がいますが、札幌の北海道血液センターの扱い分は約16万人で、半分はこちらが窓口になっているようです。ちなみに、全国では540万人の献血者数ですので、全体の6%。人口の比率に比較的近い関係にあるようです。このコラムを書いている時に、献血者の約1%に健康被害が出ているとの記事もありました。慎重な作業を望みたいところです。
父親は心臓手術中に亡くなりました。訴訟にすると面倒なので、結局、医療ミスにはしませんでしたが、ひどいものでした。心臓の裏に傷を付けて血が止まらなくなったというのです。緊急輸血が必要になりました。ですが、父はAB型で、私はA型なのです。結局、会社の同僚・後輩のみなさんの協力を得ましたが、助かりませんでした。献血の大切さを思いました。(2005.11.04)
<超高齢社会は価値観の転換が必要だ>
超高齢社会である。私はまだ50代であるが、近親者は60代、70代、80代で、本当に年寄りばかりである。子どもがいないことは別段、寂しくはないが、若い世代の声が身近で聞けないのは精神衛生的にはよろしくない。高齢者の場合は健康のことやらだれかれがどうしたのと、どうしても話題が内向きになってしまうからである。90いくつかで亡くなった本家筋の隣のおばあさんは「年寄りの話は聞きたくない。若い者がいい」と、孫やひ孫たちとの新鮮な会話を楽しんでいたものだ。
新聞では編集委員が中心になった連載「子どもがいなくなる−北海道あすの課題 第一部」もスタートした(第1部は11日で終了)。全国を上回るハイペースで進む少子・高齢化に見舞われている北海道の近未来がどうなるのか。データで裏づけを取りながら、課題を探ろうという意欲作である。子どもが生まれなくなると、学校は消えていき、教育環境が低下するのみならず、地域の疲弊が進むことは明らかだ。だが、一方で子どもを産みたくない人や産めない社会事情もある。意識の変化は制度をいじるだけでは簡単には戻らないのである。
私たちの親世代では10人前後のきょうだいが普通だった。私たちになると3人前後となり、私たちの子の世代では1人前後という感じだ。少子化により兄弟げんかが消え、子ども社会の経験の継承もなくなる。一方で、親子の確執は増すだろう。経済生活レベルでの豊かさが増したことは間違いないが、社会の豊かさはずいぶん失われた。
独り暮らしの実母は公的介護が頼りである。独り暮らしに近い義母は84歳なので介護認定を受けたのを機に、ヘルパーさんに週2回来てもらうよう手続きをした。そのためには膨大な契約書類があって、とても老人が1人で書けるものではないので、代理人として私が判を押した。母の世代は私たちがいるからいいが、私たちには子どもがいないので、自分でなんとかしなければならない。
先日、「未使用の火葬場 焼却炉に2遺体 福井・夫婦心中か」(11月9日朝刊)という記事が載っていた。それによると、福井県大野市七板の使用されていない火葬場の焼却炉で白骨化した2遺体が見つかった。2人は80歳の夫と82歳の妻で、心中を図ったものらしい。自宅からは「妻とともに逝く」と書いた夫の日記が見つかったからだ。2人はまきで火をおこした焼却炉に一緒に入り、中から扉を閉めて焼身自殺したとみられる。近所の住民によると、妻は寝たきりの状態で、夫が看病をしていたが、最近は体調を崩していたという。
涙なしには読めない記事だった。他人事ではないと多くの人が感じただろうと思う。高齢社会の話になると、やはり内向きになってしまう。老人力という言葉が流行ったが、ああいう、あっけらかんとした楽天性を大切にしたい。同じように、パラダイム・チェンジという言葉も流行ったが、ものの見方、社会のあり方を変えなくてはならない。その主役はまさに高齢世代となる団塊の世代であり、私たちに託された課題でもある。
(「朝は4本、昼は2本、夜は3本足の生き物は」というなぞなぞありましたね)
【いまさら探検隊】★★☆
<19>「北海道神宮頓宮」=中央区南2東3

札幌の古書籍商組合が定期的に開くセリ市が、中央区南2東3の屯宮神社で毎月第3水曜日に開かれているそうだ。神社で古書の入札をしているとはまことに意外である。しかも、屯宮神社はわが家のご町内である。その身近な場所が知の宝庫になっていることに驚いた。そこでは9月には秋祭りもあり、創成川東岸エリアに住む子ども(いや善男善女というべきか)には小さいながらも地域に密着している場所なのである。
屯宮神社は北海道神宮頓宮というのが一般的だ。札幌っ子にとっては欠かすことのできない初夏の一大イベント「札幌まつり」(北海道神宮例祭)で、市内を練り歩くみこしがひと休みする場所だ。北海道神宮のHPを見ると、「明治11年6月15日の例祭には、札幌中教院・神道事務局(現在の北海道神宮頓宮=中央区南2条東3丁目)開設の神事が斎行され、札幌神社の祭神と中教院の四神の神霊をそれぞれに招き、神輿一基が市街地をご巡幸した。これが渡御(とぎょ)の始まりです」とある。まさに、頓宮なくして札幌まつりはあり得ないのである。
私はわが家から自転車でサッポロファクトリーに行く途中に神社の前を通る。11月は酉(とり)の市で、それを伝えるのぼり旗も、この季節には立っている。別にお祓いをしてもらっているわけではないので、通り過ぎるだけではなんのご利益もない。それでも、寺社というものは仏教、神道、キリスト教を問わず、本来は神の依り代でありながら、昔から市が立ったり、とても人間くさい場所であると思う。(2005.11.11)
【いまさら探検隊】★
<20>「本陣狸大明神社」=中央区南2条西5丁目

札幌の商店街と言えば、アーケードのある狸小路が老舗です。私は休日になると、創成川の下をくぐって1丁目から6丁目あたりをうろちょろしています。雨の日は会社に行く時は少し遠回りになりますが、狸小路を歩きます。そんな大好きな狸小路ですが、商店街としては130年を超える歴史を持つのだそうですから、すごいですね。
「さっぽろ文庫」の第36巻が「狸小路」特集です。同書によれば、狸小路のルーツは明治4年(1871年)に開拓使本庁が札幌に移り、南1条から3条までの街並みが形成されたのが始まりだそうです。もっとも、かわいらしい愛称は別のようです。薄野がお上公認の遊郭街であったのに対して、隣接して非公認のエリアができた。白首のきれいな女性たちが出没し、それが人をはやして楽しませるが、ちょっと尻尾も出す狸に擬され、そのあだ名がそのまま本名となり、狸小路となったそうです。
明治の狸小路の3大キーワードは「白首屋」「寄席」「勧工場」とのこと。今風に言えば、セックス&エンターテインメント&ショッピングでしょうか。とりわけ、勧工場はデパートやスーパーマーケットの先駆けのようなものですから、そりゃあ魅力的だったと思われます。楽しそうだなあ。ちょっと、いかがわしいけれど、わくわくするというのが狸小路なのです。いいじゃないですか。
ちなみに「わたしゃ さっぽろね 狸小路の 生まれよ 色が黒いが 情がある」なんて「狸小路ばやし」(昭和29年、ほしはまさくら作詞)もあったそうです。今は、「ぽんぽこサンバ」のほうが有名ですが。これは余談ですね。
どの街にも栄枯盛衰があります。大型店の札幌進出に攻められましたし、最近は郊外のショッピングセンターや札幌駅前ゾーンが商業地として興隆しています。狸小路は何度目かの正念場を迎えているかもしれません。でも、セックス(これは広い意味ですよ、念のため)&エンターテインメント&ショッピングの3大キーワードをうまく展開するともっと可能性があると思います。
狸小路5丁目には、シンボルの狸をまつった神社があります。能書きによると、「大福帳をなぜると商売繁盛」「お腹をなぜると安産」とか狸の8徳があるそうです。本当かどうかわかりません。狸ですから、案外、だますことがあるかもしれませんし。開運おみくじもありますが、どうなんでしょう。近隣にはパチンコ店が増えましたが、私の場合、あまりご利益は顕著ではありませんね。それもご愛嬌だと思っています。(2005.11.18)
【いまさら探検隊】★
<21>「北海道庁 赤れんが庁舎」=中央区北3西6

私は大きいものが苦手であります。国家権力とか、グーンと落ちて北海道庁。なんだかなあ、ですが。官僚制というものは、人間に対して優しくありません。その制度が欲しているのは秩序と効率ですからね。逸脱とか越境性を魅力的に感じてきた私のような一庶民としてはありがたすぎて近寄りたくない。でもね、木陰ができ池があったりしていると、いいなあ、と思ってしまうです。とりわけ、観光スポットの「赤れんが庁舎」。レトロです。落ち着きますから、困ってしまいますよね。
さて、その赤れんが。ものの本によると、米国マサチューセッツ州議事堂をモデルにして明治21年(1888年)にアメリカ風のネオ・バロック様式で建てられたとのこと。明治期を代表する建物なのだそうです。庁舎北側には「開拓使本庁舎跡」の石碑もあるようです。道庁の本庁舎として使われていましたが、今は北海道立文書館などとして使われています。
そんな由緒ある建物ですから、札幌駅前通りから大通りへ北3条の角を右に折れると銀杏並木が続いています。なんでも、これは本道初の並木。その道路は初の舗装道路であるそうです。確かに、なかなか趣きがあります。車も公園のような道庁にぶつかりますので、直進できず左折して大通方向に抜けねばなりません。
池には野鳥が遊び、立派な彫刻も並んでいます。ぜいたくです。一般市民や観光客もブラブラ歩くことができますが、役所の一部ですから、個人的には今ひとつ落ち着きませんね。隣に現在の道庁の建物(結構古いですが)があって、業者やら手続きの道民が慌しく行き交いますし、近くには北海道警察もあります。世俗のセコセコ(コセコセ?)感が、赤れんが庁舎の風格に似合いません。「泥中の蓮」とか「掃き溜めの鶴」とか、いろいろな言い方がありますが、やはりいいものはそれなりの場所にあったほうがいいですね。
(2005.11.25)
勝手にweb「つぶやき」と「いまさら探検隊」4 へ
■トップページに戻る
